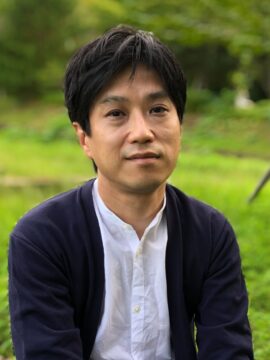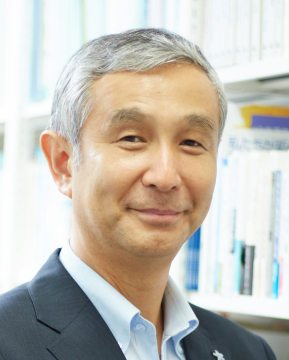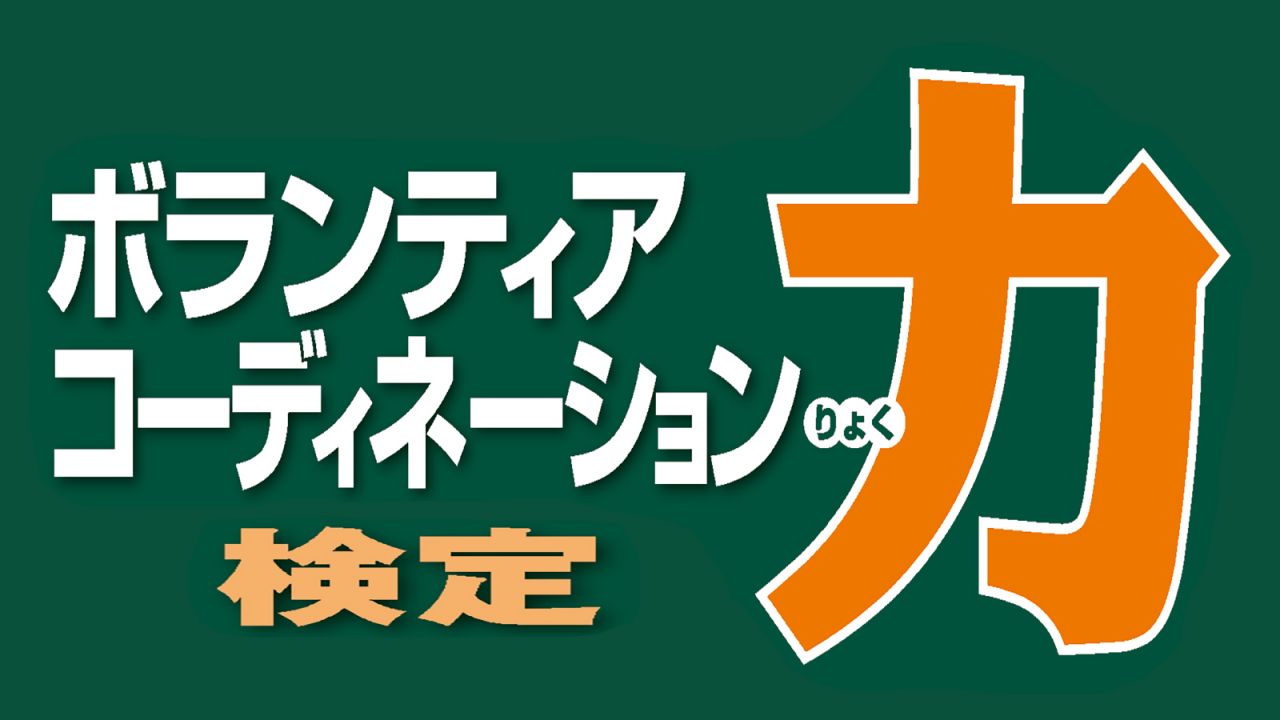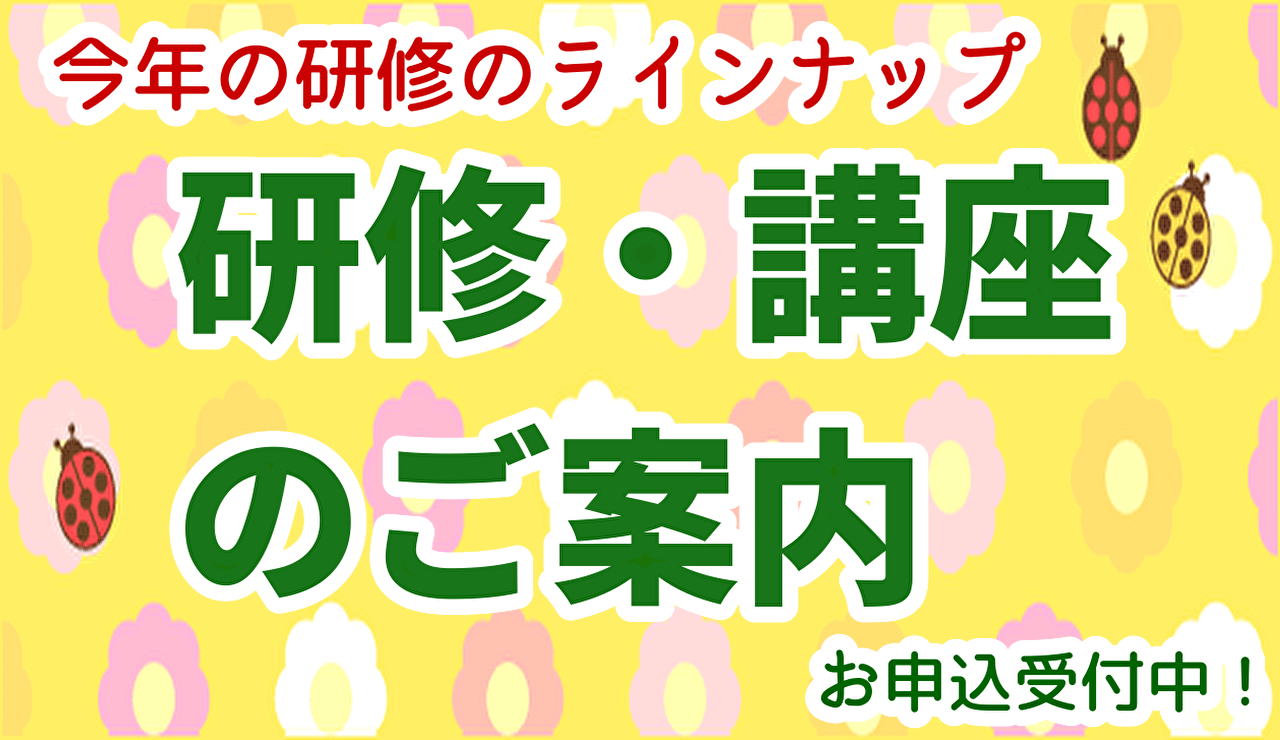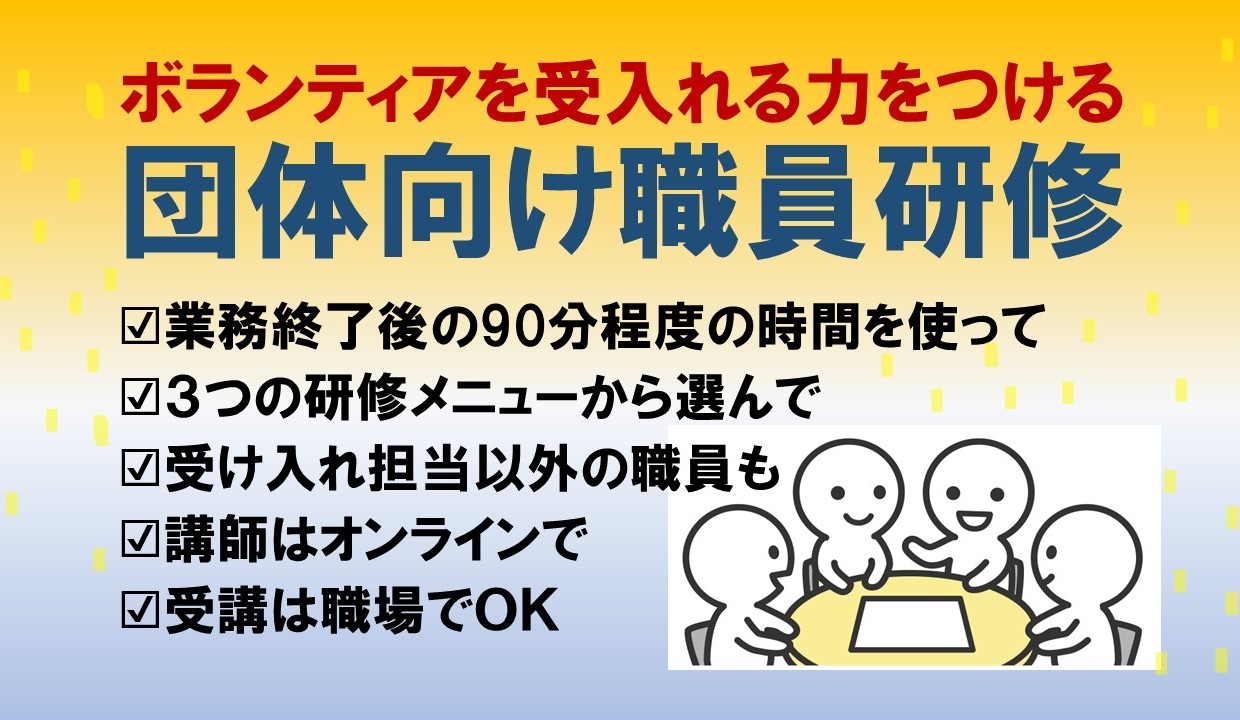Ⅱ.講師リスト
この講師リストは認定特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会が実施する[講師派遣事業]にかかわる関係者を一覧にしています。氏名の【五十音順】にプロフィールと担当できる研修・講座を例示しました。
| 講師名 | プロフィール | 担当講座例 |
|
青山 織衣 |
大阪府岸和田市生まれ。現在に至るまでずっと同市在住。 ★出発地 大阪府 |
①今こそ見つめるボランティア・地域活動の価値~コロナ後、もう一度つながりを結びなおすために~ ②ひとりひとりの力を生かして仲間を増やすには~メンバーを大事にするボランティアマネジメント~ ③「まちづくり」に寄与する福祉施設・文化施設とは~越境することで見えてくる新たな価値~ ④ボランティアコーディネーション入門~人と人とを「つなぐ」とは~ ⑤始めてみませんか?ファンドレイジング~団体のファンを増やすために~ ⑥気持ちよく活動するためのコミュニケーション術~傾聴と共感的理解を大切にしたチームづくり~ |
|
池田 幸也 |
小・中・高校の教員を経て大学院で教育社会学・ボランティア学習論を学ぶ。元常磐大学コミュニティ振興学部及び大学院教授。現在は、福祉のまちづくり、学校における総合的な学習の時間の推進、多文化共生の地域づくり、市民参加のためのネットワーキングの形成など、コーディネーション理念を踏まえたワークショップ形式の研修でファシリテーターを行っている。 ★出発地 東京都(八王子市)または茨城県(水戸市) |
①ボランティアボランティア活動における学びのコーディネーション(主体的社会的アイデンティティ形成の支援) ②学校・地域の連携による学びのコーディネーション(コミュニティスクールの推進) ③「総合的な学習の時間」の意義を活かしたコーディネーション(学校における体験学習の支援) ④市民参加を誘うコーディネーション(市民社会をめざす啓発) ⑤生活支援体制整備事業を活かした地域づくりのコーディネーション(地域福祉の推進) |
|
石井 祐理子
|
大学卒業後大阪ボランティア協会に就職し、ボランティアコーディネートを担当する。ボランティアの支援やマッチングの難しさに悩むが、ボランティアコーディネーター同志の情報交換や学び合いに支えられ、そうした「つながり」の重要性に気付く。協会退職後は、ボランティアコーディネーターの養成や現任研修などに携わりながら、ボランティアコーディネーターの“頑張り”を応援し、その“頑張り”にパワーをもらっている。 ★出発地 京都府 |
①ボランティアの入門講座 ②ボランティアコーディネーションの基礎 ③ボランティアコーディネーターの相談援助について ④ボランティアプログラムの企画 |
|
岩井 俊宗
|
1982年生まれ。栃木県宇都宮市出身。2005年宇都宮大学国際学部卒業後、ボランティアコーディネーターとして宇都宮市民活動サポートセンター入職。NPO・ボランティア支援、個別SOSに従事。2008年より若者の成長の機会創出と持続的に取り組む人材を輩出し若者による社会づくりの促進を目的に、とちぎユースサポーターズネットワークを設立。2010年NPO法人化。代表理事を務める。その他、文星芸術大学非常勤講師、他多数。 ★出発地 栃木県 |
①若者を巻き込むボランティアコーディネーション ②社会課題解決を仕事にするソーシャルビジネス起業・創業 ③地域の課題を解決していくボランティアプログラムの作り方 ④NPOの経営、組織マネジメント |
|
上田 英司
|
島根県出身。NPO法人NICEの事務局長を経て、現在、日本NPOセンター事務局次長。狛江市市民活動支援センター運営委員長、早稲田大学Life Redesign College講師などを務める。企業とNPOの協働事業やボランティアコーディネーションを専門として、市民参加の推進に取り組む。 ★出発地 東京都 |
①若者の参加・参画を促すボランティアコーディネーション ②社員参加型のボランティアコーディネーション ③少子高齢化を抱える地域でのボランティアコーディネーション ④ボランティア活動の評価 |
|
小野 智明
|
神奈川県社会福祉協議会にて研修部門、企画部門を経て8年間ボランティアセンターに勤務。主にボランティアコーディネーションやセルフヘルプ活動支援に関わる業務を担当。現在は保育者とボランティアの協働について研究中。 ★出発地 神奈川県 |
①社会福祉施設におけるボランティアコーディネーション ②社会福祉協議会におけるボランティアコーディネーションの基礎 |
|
小原 宗一
|
1989年より北区社会福祉協議会に勤務し、ボランティアセンターの運営に携わりながら、全国のJVCC実行委員らとともに日本ボランティアコーディネーター協会(JVCA)の設立に参加する。現在、北区社協勤務のかたわら日本ボランティアコーディネーター協会にて研修や検定システムの開発に関わる。現在はボランティアコーディネーション力検定試験委員(1級検定チームリーダー)、研修開発委員。 ★出発地 東京都 |
①ボランティアコーディネーション概論 ②ボランティアマネジメント研修(基礎編、実践編) ③ボランティアセンター運営研修 ④ボランティアグループ運営研修 ⑤ボランティアセンター運営診断研修 ⑥中間支援組織向けボランティアマネジメント支援研修 ⑦社会福祉協議会ボランティアセンター新人研修
|
|
鹿住 貴之
|
1972年生まれ。学生時代に、とうきょう学生ボランティアふぉーらむ、早稲田大学学生ボランティアセンターの設立に参画し、代表を務める。98年大学生協の呼びかけで設立された都市と農山漁村を結ぶJUON NETWORK(樹恩ネットワーク)に事務局スタッフとして参画。99年3月より事務局長。その他、淑徳大学兼任講師、NPO法人森づくりフォーラム常務理事、認定NPO法人エンパワメントかながわ理事、杉並ボランティアセンター運営委員等様々な市民活動に携わっている。著書に『割り箸が地域と地球を救う』(創森社・共著)等。 ★出発地 東京都 |
①市民参加の森づくり ②市民参加の環境保全活動 ③ボランティア講座 ④ボランティアコーディネーション基礎研修 ⑤企業市民活動の推進について |
|
唐木 理恵子
|
2011年10月まで東京都内の社会福祉協議会ボランティアセンターで、22年間ボランティアコーディネーターとして勤務、在職中は、複数の窓口で毎月実施していたケース検討にスーパーバーザーとして携わる。2001年の日本ボランティアコーディネーター協会創設時からメンバーとしてかかわり、一貫してボランティアコーディネーターの社会的な認知の向上に関する活動や、資質向上のための研修等を担当。東京ボランティア・市民活動センター中間組織スタッフの支援力アップ塾企画・評価委員。 ★出発地 東京都 |
①ボランティアコーディネーションの基礎 ②ボランティア概論 ③中間支援組織のボランティアコーディネーションの基礎 ④ボランティアセンターにおける相談対応(相談援助技術) ⑤ボランティアセンターにおける相談対応(事例検討) ⑥ボランティアセンターにおける相談対応(記録の取り方、活かし方) ⑦ボランティアマネジメントの基礎(施設・団体のボランティア受入) |
|
菊池 哲佳
|
2000年に仙台国際交流協会(現・仙台観光国際協会)に入職後、主に外国人相談、地域日本語教育、外国につながる子ども支援、防災事業に携わり、地域の多文化共生推進に取り組む。2011年の東日本大震災では、仙台市が設置した「災害多言語支援センター」でボランティアコーディネートを担うなど、外国人被災者の支援に従事した。本務のほか(一社)多文化社会専門職機構事務局長を務める。多文化社会コーディネーター(多文化社会専門職機構認定)。 ★出発地:宮城県仙台市 |
①災害時通訳・翻訳ボランティア研修 ②国際交流・協力分野でのボランティアコーディネーション ③多文化共生時代のボランティアコーディネーション |
|
栗原 穂子
|
山形県鶴岡市在住。社会福祉協議会のボランティアセンター等でボランティアコーディネーター業務を経て、ぼらんたすの設立に参加。「ボランタリー」「ボランティア」をキーワードに地域の中の課題解決に向けたイベントを開催し、人任せにしない地域づくりに取り組む。東日本大震災大震災におけるJVCAでの福島支援活動では、JVCA福島事務局として従事。「福祉共育をすすめるための検討会」、「庄内地域自殺予防対策に関する関係者会」(山形)のメンバーとして参加。ボランティアコーディネーション力検定1級合格。 ★出発地 山形県 |
①ボランティア入門講座~ボランティアはじめの一歩~ ②ボランティアリーダー養成講座 ③ボランティア研修・講座の企画作りや運営 |
|
後藤 麻理子
|
東京都社会福祉協議会に入職後、高齢者の職業・生活相談業務、東京ボランティアセンターにおける相談・情報活動・企業の社会貢献活動推進・地区ボランティア活動推進等を担当し、その後都内北区ボランティアセンターに出向して地域のボランティア活動推進や地域福祉活動計画などの策定に携わった。全国の仲間とともに2001年日本ボランティアコーディネーター協会を設立。翌年4月事務局長に就任し、2005年からは専従となる。ボランティアの力を原動力とする組織(JVCA)の事務局長として、ボランティアと協働で事業と運営を進める参加型のマネジメントスタイルを実践している。 ★出発地 東京都 |
①ボランティアマネジメントの基礎(施設・団体のボランティア受入) ②ボランティアコーディネーションの基礎 ③ボランティア受入におけるリスクマネジメント ④ボランティアプログラム開発 ⑤ボランティアを受け入れるための基盤整備(環境づくり) ⑥ボランティア基礎講座 ⑦中間支援組織のボランティアコーディネーションの基礎 ⑧ボランティア交流会のファシリテート |
|
佐藤 匠 |
1992年福島県福島市生まれ。大学入学年に東日本大震災を経験。これをきっかけに、これまであまり関心が無かった「ボランティア・市民活動」の世界に入り込み、そこで人と人が関わり、何かを創り上げていくボランティアの「面白さ、楽しさ」を実感する。学生時代は、主に子ども支援の活動に関わり、大学卒業後は、社会福祉協議会に入職。障害分野、児童分野及び広報の業務に携わる。2019年から、至学館大学。2022年からは、学生と地域をつなぎ学びに発展させる教育活動にコーディネーターとして従事。JVCAでは、理事・運営委員を務める。ボランティアコーディネーション力検定2級合格。 ★出発地 愛知県名古屋市 |
①ボランティア入門講座 |
|
土崎 雄祐 |
1988年秋田県生まれ。大学卒業後、栃木県内の市民活動支援センター職員としてキャリアをスタートし、現在は非営利組織の経営や大学勤務をしつつ、市民活動や地域づくり支援を行っている。近年の関心テーマは地域防災、中山間地域の活性化、子ども支援、学校魅力化など。主著に『はじめての地域づくり実践講座:全員集合!を生み出す6つのリテラシー』(分担執筆)、『はじめての地域防災マネジメント:災害に強いコミュニティをつくる』(分担執筆)。趣味は某アイドルの追っかけ。公職として、那須塩原市男女共同参画審議会会長、佐野市市民活動推進委員会委員、とちぎ協働アドバイザーなど。准認定ファンドレイザー、ボランティアコーディネーション力検定1級合格、社会教育士。 ★出発地 栃木県 |
①ボランティア・社会参加の基礎(子ども向け、シニア向け) ②ボランティアコーディネーションの基礎 ③中間支援組織におけるボランティアコーディネーション ④市民活動団体・地縁組織における団体運営 ⑤市民活動団体・地縁組織における会議の進め方 ⑥ファンドレイジングの基礎 ⑦市民協働推進に向けた心技体 |
|
筒井 のり子
|
龍谷大学社会学部教授。関西学院大学大学院生の頃から7年間、地域福祉を推進する市民活動団体の事務局長として運営に携わるとともに、コミュニティワーカー、ボランティアコーディネーターとして実践を積む。その後、いくつかの大学を経て1999年より現職場。日本ボランティアコーディネーター協会設立の準備段階からの参画し、2004年~2007年度、2012年〜2015年度に代表理事を務める。 ★出発地 大阪府 |
①ボランティアとは 〜ボランティアの価値と果たすべき役割〜 |
|
長沼 豊
|
中学校教諭を経て大学教員に、その後中学校校長も兼務。高校時代からボランティア活動に取り組み、ボランティア団体における組織マネジメントやレクリエーションについて興味をもつようになる。教育とボランティアの接点を探り続け、福祉教育・ボランティア学習におけるコーディネーションについて講演やワークショップを各地で行う。著書は『学校ボランティアコーディネーション』『人が集まるボランティア組織をどうつくるのか ~「双方向の学び」を活かしたマネジメント~』など多数。日本レクリエーション協会公認「レクリエーションコーディネーター」 ★出発地 東京都 |
①福祉教育・ボランティア学習におけるボランティアコーディネーション ②ボランティア組織のマネジメント ③グループワークの進め方 ④アイスブレークの技法・伝達技法 ⑤学校づくり&まちづくり ⑥親子ではじめるボランティア(子どもの自己肯定感を育てる) ⑦イエナプラン教育と市民性、ボランティア ⑧部活動におけるボランティア、地域展開とまちづくり |
|
西川 正
|
学童指導員、出版社などを経て、2005年、ハンズオン埼玉を設立。「おとうさんのヤキイモタイム」キャンペーンなど、協働・市民参加型のまちづくりのプロデュースに関わる。 地元では、PTA、民生委員、自治会、学童保育などにかかわり地縁と志縁の間を行き来きしつつ、様々な提案と実践を重ねる。 ★出発地 埼玉県または岡山県真庭市★JVCAでの役職 元理事 |
①市民参加・公共施設と場づくり・まちづくり ②地縁・地域活動の活性化 ③PTA・保護者会の活性化 など |
|
早瀬 昇
|
1955年、大阪府生まれ。大学で電子工学科を専攻するも、学生時代に交通遺児問題、地下鉄バリアフリー化問題などに関わる市民活動に次々に参加。卒業後、フランス・ベルギーの福祉施設で研修後、78年に大阪ボランティア協会に就職。91年~2010年まで事務局長。他に大阪大学人間科学部と関西大学経済学部の客員教授なども務める。ビートルズをこよなく愛する赤ワイン党。大の阪神タイガースファン。 ★出発地 大阪府 |
①ボランティア活動の進め方 ②市民活動団体の参加型運営 ③ファンドレイジングの進め方 ④市民活動に関する法人制度、税制度の解説 ⑤市民活動と行政の協働の進め方 ⑥企業市民活動の推進について |
|
疋田 恵子
|
1994年杉並ボランティアセンターへの異動をきっかけにボランティアコーディネーションに携わる。NPO支援、住民による地域福祉活動の推進、個別支援を中心とした「福祉なんでも相談」「生活困窮者自立支援事業」等幅広く担当。東日本大震災における被災地支援活動として、福島支援にも参加。他に、日本ファシリテーション協会に参加。 ★出発地 東京都 |
①ボランティアコーディネーションの基礎 ②ボランティアマネジメント研修 ③福祉施設ボランティア担当者交流会 ④ボランティア活動の効果・意義の可視化プログラム ⑤異世代協働のコツ ⑥生活支援コーディネーター向けファシリテーションの基礎 |
|
南 多恵子
|
1992年大阪ボランティア協会に就職。ボランティアコーディネーターとしてボランティア講座や月刊誌編集、個別のボランティアコーディネーション業務などに従事する。その後、専門学校、短大、そして、高齢者福祉施設を運営する社会福祉法人での勤務経験を経て2013年から現職。 ★出発地 京都府 |
①社会福祉施設の担当者向けボランティアコーディネーション基礎 |
|
妻鹿 ふみ子
|
大阪ボランティア協会勤務の後、専門学校講師、京都光華女子大学等を経て2011年より現職。専門は地域福祉論、ボランティア論、NPO論等。 ★出発地 東京都 |
①ボランティアマネジメントの基本 ②ボランティアコーディネーション基礎 ③ボランティアプログラム開発 ④ボランティアグループリーダー研修 ⑤地域住民のささえあいのしくみやシステムの構築 ⑥福祉施設の地域貢献 ⑦文化施設のためのボランティアマネジメント ⑧多文化共生とコーディネーション |
|
矢島 万理
|
2006年から11年間、身近な自然環境の保全をミッションとしたNPOに所属。東京都西部エリアの公園で、ボランティアコーディネーターとして人と自然、人と人をつなぐ活動に取り組む。雑木林や花壇など身近な自然を対象としたボランティアコーディネーション、地域と連携したイベントの企画運営、協働型パークマネジメントの構築を担う。2019年から現職。森林空間の活用について、様々な地域と共に考えている。 ★出発地 東京都 |
①森林ボランティアのためのボランティアコーディネーション ②公園とまちづくりにおけるボランティアコーディネーション ③地域課題の解決策としての森林空間利用
|